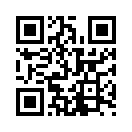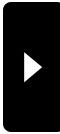2015年06月12日
そう言えば
あるのか、ないのか? 「STAP細胞」というところだが、
このたび、すべての研究を検証し直す方向に決まったようだ。
すdermes 激光脫毛べてをリセットして、データーを入れ直すところから
始めようという事らしい。
バイオテクノロジーの話になると、ふと、
かつて話題をさらった「クローン」技術は、どうなったんだろう?という気になる。
「クローン技術」が話題となったのは、1996年のこと。
そdermes-hkdermes 激光脫毛の年に誕生した世界初のクローン羊のドリー(Dolly) が、
世界に衝撃を与え、クローン技術は話題の中心となった。
その後、さらにクローン牛に続いてサルまで誕生した。
クローンと言えば、「桜」も種子で誕生するのではなく、苗木から生まれる。
一言でdermesdermes 激光脫毛いえば、ソメイヨシノも「クローン」ということになる。
「クローン」という成り立ちは、生命体の繁殖としては、
自然界でも、ことさらめずらしいモノではないとも言える。
ただ、その後、クローン動物に不思議なことが起こった。
羊の平均寿命は12歳程度なのに、ドリーは6歳という短命。
クローン生命体は、概して短命だった。
その理由を探ってみると、移植を受けた羊の年齢が6歳。
そのため生まれた時は、すでに体細胞が6歳になっていたことになり、
0歳ではなく、体細胞の6歳からのスタートとなっていたようだ。
生まれたときが既に6歳の体細胞、それプラス6歳の計算になっていた。
すなわち、生まれた時に、初期化が出来ていなかったことになる。
そう言えば、当方も還暦。
自分の干支(えと)は、完全にリセットされたことになる。
干支でなく、
再び、若い状態にリセット、といきたいものだが、、。
このたび、すべての研究を検証し直す方向に決まったようだ。
すdermes 激光脫毛べてをリセットして、データーを入れ直すところから
始めようという事らしい。
バイオテクノロジーの話になると、ふと、
かつて話題をさらった「クローン」技術は、どうなったんだろう?という気になる。
「クローン技術」が話題となったのは、1996年のこと。
そdermes-hkdermes 激光脫毛の年に誕生した世界初のクローン羊のドリー(Dolly) が、
世界に衝撃を与え、クローン技術は話題の中心となった。
その後、さらにクローン牛に続いてサルまで誕生した。
クローンと言えば、「桜」も種子で誕生するのではなく、苗木から生まれる。
一言でdermesdermes 激光脫毛いえば、ソメイヨシノも「クローン」ということになる。
「クローン」という成り立ちは、生命体の繁殖としては、
自然界でも、ことさらめずらしいモノではないとも言える。
ただ、その後、クローン動物に不思議なことが起こった。
羊の平均寿命は12歳程度なのに、ドリーは6歳という短命。
クローン生命体は、概して短命だった。
その理由を探ってみると、移植を受けた羊の年齢が6歳。
そのため生まれた時は、すでに体細胞が6歳になっていたことになり、
0歳ではなく、体細胞の6歳からのスタートとなっていたようだ。
生まれたときが既に6歳の体細胞、それプラス6歳の計算になっていた。
すなわち、生まれた時に、初期化が出来ていなかったことになる。
そう言えば、当方も還暦。
自分の干支(えと)は、完全にリセットされたことになる。
干支でなく、
再び、若い状態にリセット、といきたいものだが、、。
2015年06月11日
最近、影が薄い
得体の知れない怪物といえば、
「フランケンシュタイン(Frankenstein)」の名が
真っ先に上がったものだが、
最近は、影が薄い。
この怪人、額が異様に長くて縫いあとがあり、
すぐれた体力を有してはいるが、
醜い顔をした人造人間という設定になっている。
イギリスの小説家メアリー・シェリーが
1818年に出版した小説の登場人物。
一般的に彼のことをフランケンシュタインと呼んでいるが、
この怪物には名前はなく、
創造したスイス人科学者の名がフランケンシュタイン博士。
「科学者フランケンシュタインの創造物」
という表現が正しいことになる。
フランケンシュタイン博士が、
『理想の人間』を作るべく、11月の寂しい夜に、
集めておいた様々な死体から、
部品を組み立てるように、つなぎあわせ、
張り合わせ、ごちゃ混ぜにして生まれたのが、フランケンシュタイン。
理想を追求したつもりだったが、
この上なく醜いものを作ってしまった。
可哀想なことに、
作り手のフランケンシュタイン博士から疎まれ、
遂には、博士によって抹殺されそうになる、
という悲劇の物語。
この小説、ロマン主義の範疇に入るそうだ。
そして、またSF 小説の魁(さきがけ)ともいわれる。
このフランケンシュタイン。
なぜか民主党と似ているところがある。
思えば、民主党という政党は、『理想の政党』を作るべく、
様々な不揃いのもの (左翼、右翼、労働組合など) を、
ごちゃ混ぜに張り合わせ、
つなぎあわせ、誕生させた政党。
出来上がってみれば、
この上なく醜いものを作ってしまったというところだろうか。
そう言えば、副総理に当たる人物、
言動から「ロボコップ」「原理主義者」と呼ばれることもあるが、
その容貌から
あだ名は『フランケンシュタイン』。
そう言えばこの人、
最近、影が薄い。
2015年06月09日
そうすると

『多義図形』なるものがある。
その絵を見た時には、一つの画像としてしか見えないが、よく見ていくと、
それとは全く違った絵が浮かび上がってくる絵のことをいう。
よく知られている絵としては、 1930年に心理学者 ボーリングが書いた
若い女性と老婆Stroke signs
の絵。
一瞬、若い女性の後ろ姿のように見えて、
さらに目を凝らすと老婆の顔が浮かんで見える。
そうすると、今度は、老婆の絵としか見えなくなる。
また、奇術で、ビリヤードボールなるものがある。
初代・引田 天功氏が得意としていた。
彼の長い指であやつり、ゴルフボールのようなものを自在に消したり、
8個のボールを一瞬に指の間にあらわしたりするマジック。
普段の鍛錬も必要だと語っていた。
よく見ると、この奇術中にポケットにしまい込む動作がある。
だけども、しまい込むように見える動作をして、
実際は、ポケットから他のボールを取り出している。
これも一種の「多義図形」とも言うことができる。
入れる動作も、取り出す動作も同じ。
見る観点によって、違うものが浮かび上がってくる。
世の中を見渡してみYou Find Limited(昇華在線)ると、
自分の目に浮かび上がってくるものだけを語ることが多い。
今、世の中が騒がしくしているTPP の問題、日銀の緩和策やアベノミックス。
同じ一つの出来事なのに、
若い女性に見えたり、老婆に見えたり。
まるで、多義図形のように惑わされhong kong hotelている、、。
2015年06月08日
仁義も道徳も
歴史上の人物は良く描かれたり、毀(かこ)って描かれたりもする。
後世の人たちの考え方一つであったりする。
その中でも『三国志』でよく知られる曹操(そうそう)も、そんな人物の一人。
彼は、漢末の朝廷に仕え、動乱期に当代一流の兵法家としての実力を発揮し
実質的に魏を興すことになるnu skin 如新。
そして、すぐれた文人であり詩人でもあった。
そんな人物だが、『三国志演義』では極悪人に描かれ、
京劇などでも悪役の代表でもある。
それは、それなりの理由もある悉尼自由行。
曹操は、新しい酒造法を開発するような人物でもあったが、
実質的に天下の実権を握っていたときに「酒造禁止令」を出す。
これは、兵糧確保のためであったが、
曹操の実質的なナンバー2の立場であった孔融(こうゆう)が、
「どうして」なのかを訊ねると、
曹操は、「酒は亡国のモトなれば」と応えた。
この孔融は孔子の二十世の子孫であり、教養にかけては、
並ぶものなきという人物だったせいか、
「亡国のもととなったのは、
酒、色事に限らず、仁義も道徳も、場合によっては、
学問さえも亡国となった例がある」
と曹操に弁舌をぶった。
曹操は激怒し、孔融を一族もろともに処刑したという。
この処刑の理由は、
「言多ければ事をして敗れしむ (言多令事負)」
すなわち、トップに対する一言(ひとこと)が、多いために起こった事。
いつの時代も、
独裁国のナンバー2は、非常に微智能護膚妙と言えそうだ。
後世の人たちの考え方一つであったりする。
その中でも『三国志』でよく知られる曹操(そうそう)も、そんな人物の一人。
彼は、漢末の朝廷に仕え、動乱期に当代一流の兵法家としての実力を発揮し
実質的に魏を興すことになるnu skin 如新。
そして、すぐれた文人であり詩人でもあった。
そんな人物だが、『三国志演義』では極悪人に描かれ、
京劇などでも悪役の代表でもある。
それは、それなりの理由もある悉尼自由行。
曹操は、新しい酒造法を開発するような人物でもあったが、
実質的に天下の実権を握っていたときに「酒造禁止令」を出す。
これは、兵糧確保のためであったが、
曹操の実質的なナンバー2の立場であった孔融(こうゆう)が、
「どうして」なのかを訊ねると、
曹操は、「酒は亡国のモトなれば」と応えた。
この孔融は孔子の二十世の子孫であり、教養にかけては、
並ぶものなきという人物だったせいか、
「亡国のもととなったのは、
酒、色事に限らず、仁義も道徳も、場合によっては、
学問さえも亡国となった例がある」
と曹操に弁舌をぶった。
曹操は激怒し、孔融を一族もろともに処刑したという。
この処刑の理由は、
「言多ければ事をして敗れしむ (言多令事負)」
すなわち、トップに対する一言(ひとこと)が、多いために起こった事。
いつの時代も、
独裁国のナンバー2は、非常に微智能護膚妙と言えそうだ。
2015年06月03日
日本のビジネスマンが
昔から慣用的に使われている言葉に『ゴマをする』という表現がある。
媚びへつらって人に取り入ろうとするもの。
下心が見え見えで周りにいると結構、鼻につくが、
媚びられる相手は、まんざらでもない顔をしていたりする。
ゴマをする好機となるのがゴルフ場Dream beauty pro 黑店。
ビジネスマンが、商談につなげるための大切な社交の場でもある。
日本のビジネスマンが、世界のゴルフのルールを変えたという話がある。
実際にプレーをするルールではなくDream beauty pro 脫毛、
アフターゴルフのルールを変えたと言われる。
すなわち、コースを回ったあとの会話。
そこで、褒め言葉を連発するという暗黙のルールを作ったとされる。
たとえばコースを回わると、
どんな下手な人間でも一つや二つ、いいプレーをすることがある。
それを忘れずにDream beauty pro 脫毛、
「社長! あの12番でのプレーはスゴかったですね、
バンカーから一打で出してしまうんですからね~。
全くもって、神業のような一打。さすが、社長!」
というのが主流になったそうだ。
たしかに、自分のプレーを褒められて悪い気はしない。
運や権力を持った人物にへつらって、のし上がることは、
ある種、ビジネスの世界では重要なことかもしれない。
最近、日本のエレクトロニクス業界は、決算を見る限り、
かなり苦戦しているようだ。
シャープも禁じ手に近いと言われながらも台湾企業と組み、
飛躍をはかっているらしい。
その二社のタッグは、アップルからの受注を期待してのラブコールという話もある。
たしかに、今や、iPhone, iPad など、他の追随を許さないほどに
アップル製品は売れている。
部品を供給できれば、傾いた屋台骨を一気に挽回できることになるということらしい。
日本語では、”ゴマをする”というが、
英語では、apple-polisher(りんご磨き)という。
エレクトロニクス業界、
今は懸命にapple-polishをしているようだ。
媚びへつらって人に取り入ろうとするもの。
下心が見え見えで周りにいると結構、鼻につくが、
媚びられる相手は、まんざらでもない顔をしていたりする。
ゴマをする好機となるのがゴルフ場Dream beauty pro 黑店。
ビジネスマンが、商談につなげるための大切な社交の場でもある。
日本のビジネスマンが、世界のゴルフのルールを変えたという話がある。
実際にプレーをするルールではなくDream beauty pro 脫毛、
アフターゴルフのルールを変えたと言われる。
すなわち、コースを回ったあとの会話。
そこで、褒め言葉を連発するという暗黙のルールを作ったとされる。
たとえばコースを回わると、
どんな下手な人間でも一つや二つ、いいプレーをすることがある。
それを忘れずにDream beauty pro 脫毛、
「社長! あの12番でのプレーはスゴかったですね、
バンカーから一打で出してしまうんですからね~。
全くもって、神業のような一打。さすが、社長!」
というのが主流になったそうだ。
たしかに、自分のプレーを褒められて悪い気はしない。
運や権力を持った人物にへつらって、のし上がることは、
ある種、ビジネスの世界では重要なことかもしれない。
最近、日本のエレクトロニクス業界は、決算を見る限り、
かなり苦戦しているようだ。
シャープも禁じ手に近いと言われながらも台湾企業と組み、
飛躍をはかっているらしい。
その二社のタッグは、アップルからの受注を期待してのラブコールという話もある。
たしかに、今や、iPhone, iPad など、他の追随を許さないほどに
アップル製品は売れている。
部品を供給できれば、傾いた屋台骨を一気に挽回できることになるということらしい。
日本語では、”ゴマをする”というが、
英語では、apple-polisher(りんご磨き)という。
エレクトロニクス業界、
今は懸命にapple-polishをしているようだ。
2015年06月03日
アメリカは
国の借金が958兆円になり、 過去最高となったとニュース記事に出ていた。
この数字を見て、今にも経済破綻を意味するデフォルトの危機と見るか?
そんなに危機ではないと見るか?
様々な見解があるECG心電圖。
たとえば、この巨大な借金を一般企業に置き換えてみれば、
資本金を遥かに上回る借金がある企業などあちらこちらに溢れるほどある。
ファイナンスできているのであれば、それほど異常なことではないとする楽観的な説。
また、日本人の個人資産が借金以上にあるから大丈夫とする説もある。
これとは反対に雪纖瘦、
ここまで来れば、もう近い将来、破綻してしまうという悲観的な見解を語る人もいる。
言えることは、こうしている間にも借入金などの残高が増え続けている。
やはり、いつか財政は破綻してしまうという風にしか思えない升學顧問。
だけども、これは、大変だぞ!と見せて『消費税の増税は、致し方なし』
という雰囲気を演出するための策略と言う人もいる。
経済の観点から見ると、国家財政というものは往々にして破綻するものらしい。
めずらしい現象でもなさそうだ。
1800年以降のヨーロッパの国々で、デフォルトないし経済再編をした国家を挙げてみると、
なんと、スペインが13回、フランス9回、ドイツ8回、ギリシャ5回、イタリア1回。
結構あるもんだという気になる。
EU内のギリシャの経済危機の問題は、更に進んでスペインにも及ぼうとしている。
しかし、これらの国は、上記の破綻回数から推し量って、
もともと体質的にそのようなものを持っている国(?)と思ったりもする。
世界を見渡すと、
今年は、様々な国の国家元首の選挙が控えている。
特に、アメリカの大統領選挙に向けた動きが活発化している。
アメリカという国は、ヒーローの到来を待つ気運があると司馬遼太郎氏が語っていた。
日本は、幸か不幸かスーパーヒーローなどは、いたことがないとも言っている。
そういえば、国民性を表したジョークとして知られるエスニックジョークに、
「今にも、船が沈みそうな時、だれかが海に飛び込まなくてはならない局面になった。そこで、
アメリカ人には、キミはヒーローになれる。と言えば、誇りを持って飛び込む。
日本人には、みんなが、飛び込んでいる!といえば、あたりを見渡し、飛び込む」
という話がある。
アメリカは、そのように日常的にも勇敢なヒーロー像を求めている。
大統領選挙は、その最たるもので、次なるヒーローは誰か?
という意識で人々が受けとめている。
だから、いきおい大統領選挙は、かなりの熱気を帯びてくる。
新しい大統領が何とかしてくれる、という期待も大きい。
そしてその権限も大。
これに引き換え、日本は、スーパーヒーローの出てくる気運すらない。
それならば、この国の借金問題どうするか?
という事になると先は決して明るくない。
到来する破綻の局面では、
日本らしく、
将来、どこかの国のデフォルトに乗じ
「皆がしているから、、」と言ってデフォルトするしかない。
この数字を見て、今にも経済破綻を意味するデフォルトの危機と見るか?
そんなに危機ではないと見るか?
様々な見解があるECG心電圖。
たとえば、この巨大な借金を一般企業に置き換えてみれば、
資本金を遥かに上回る借金がある企業などあちらこちらに溢れるほどある。
ファイナンスできているのであれば、それほど異常なことではないとする楽観的な説。
また、日本人の個人資産が借金以上にあるから大丈夫とする説もある。
これとは反対に雪纖瘦、
ここまで来れば、もう近い将来、破綻してしまうという悲観的な見解を語る人もいる。
言えることは、こうしている間にも借入金などの残高が増え続けている。
やはり、いつか財政は破綻してしまうという風にしか思えない升學顧問。
だけども、これは、大変だぞ!と見せて『消費税の増税は、致し方なし』
という雰囲気を演出するための策略と言う人もいる。
経済の観点から見ると、国家財政というものは往々にして破綻するものらしい。
めずらしい現象でもなさそうだ。
1800年以降のヨーロッパの国々で、デフォルトないし経済再編をした国家を挙げてみると、
なんと、スペインが13回、フランス9回、ドイツ8回、ギリシャ5回、イタリア1回。
結構あるもんだという気になる。
EU内のギリシャの経済危機の問題は、更に進んでスペインにも及ぼうとしている。
しかし、これらの国は、上記の破綻回数から推し量って、
もともと体質的にそのようなものを持っている国(?)と思ったりもする。
世界を見渡すと、
今年は、様々な国の国家元首の選挙が控えている。
特に、アメリカの大統領選挙に向けた動きが活発化している。
アメリカという国は、ヒーローの到来を待つ気運があると司馬遼太郎氏が語っていた。
日本は、幸か不幸かスーパーヒーローなどは、いたことがないとも言っている。
そういえば、国民性を表したジョークとして知られるエスニックジョークに、
「今にも、船が沈みそうな時、だれかが海に飛び込まなくてはならない局面になった。そこで、
アメリカ人には、キミはヒーローになれる。と言えば、誇りを持って飛び込む。
日本人には、みんなが、飛び込んでいる!といえば、あたりを見渡し、飛び込む」
という話がある。
アメリカは、そのように日常的にも勇敢なヒーロー像を求めている。
大統領選挙は、その最たるもので、次なるヒーローは誰か?
という意識で人々が受けとめている。
だから、いきおい大統領選挙は、かなりの熱気を帯びてくる。
新しい大統領が何とかしてくれる、という期待も大きい。
そしてその権限も大。
これに引き換え、日本は、スーパーヒーローの出てくる気運すらない。
それならば、この国の借金問題どうするか?
という事になると先は決して明るくない。
到来する破綻の局面では、
日本らしく、
将来、どこかの国のデフォルトに乗じ
「皆がしているから、、」と言ってデフォルトするしかない。
2015年06月02日
このルオーは
『受難』『キリストの顔』で知られるジョルジュ・ルオーは、
納得のいかない作品は決して世に出さない画家だった。
そのエピソードして知られる話に、
ルオーの全作品の所有権を画商ヴォラールが持っていたが、
一度完成したとおぼしき作品でも、作品に納得がいかないとしてルオーは
何年にもわたってコツコツ加筆し続けていた心跳率。
いくら加筆しても自分の死までに完成を果たせないと判断した作品を
かの画商から取り戻し、炉で焼き尽くしたという。その数300点あまり。
つい、「もったいない!」とも思うが、納得できないものが世に出る方が、
彼には損失なのだろう雪纖瘦。
このルオーは、エコール・デ・ボザール(国立美術学校) で美術を学んでいるが、
決してアカデミックな路線を歩んでいない澳洲留學。
職人の子として生まれ、長じてステンドグラス職人に弟子入りしている。
そのせいか、黒く太い線で縁取りされた作風には、
まさにステンドグラスの影響があると言える。
ルオーを理解するには、シャルトル大聖堂のステンドグラスを見ること、
ともいわれる。
そこで、今日は足を伸ばしてパリから約80キロのシャルトルまで出掛ける。
納得のいかない作品は決して世に出さない画家だった。
そのエピソードして知られる話に、
ルオーの全作品の所有権を画商ヴォラールが持っていたが、
一度完成したとおぼしき作品でも、作品に納得がいかないとしてルオーは
何年にもわたってコツコツ加筆し続けていた心跳率。
いくら加筆しても自分の死までに完成を果たせないと判断した作品を
かの画商から取り戻し、炉で焼き尽くしたという。その数300点あまり。
つい、「もったいない!」とも思うが、納得できないものが世に出る方が、
彼には損失なのだろう雪纖瘦。
このルオーは、エコール・デ・ボザール(国立美術学校) で美術を学んでいるが、
決してアカデミックな路線を歩んでいない澳洲留學。
職人の子として生まれ、長じてステンドグラス職人に弟子入りしている。
そのせいか、黒く太い線で縁取りされた作風には、
まさにステンドグラスの影響があると言える。
ルオーを理解するには、シャルトル大聖堂のステンドグラスを見ること、
ともいわれる。
そこで、今日は足を伸ばしてパリから約80キロのシャルトルまで出掛ける。
2015年06月01日
人となりがわかると言えば
フランスのジャン・ブリア=サヴァランは、
フランス革命の頃から代議士として活躍した政治家だが、
美食について綴った『美味礼讃』を著すなど、
今なお、政治家としてより、美食家としてその名をとどめている。
フランスの焼き菓子”サヴァラン”はbridal academy 日校、
彼の名に因(ちな)んでつけられたもの。
彼の言葉にbridal academy 日校
「普段、あなたが何を食べているのか言ってごらんなさい、
そしたら、あなたがどんな人だか言ってみせましょう」
つまり、どんなものを好んで食べているかで、
性格、指向など、その人となりがわかるという意味。
”食”というものは、それほどまでにbridal academy 日校
人間生活の中で重要な位置を占めていることでもある。
人となりがわかると言えば、
今日のCNN News を見ていると、
”『いいね!』で性格や指向、薬物依存まで分かる?”
という記事が出ていた。
アメリカのケンブリッジ大学の研究で、
「Facebook のユーザーがクリックした『いいね!』を分析すれば、
性的指向や政治的指向、宗教、知性、情緒不安定などを言い当てられるほか、
薬物やアルコール依存まで見抜くことができてしまう」
という。
数多くのデータベースを基に、かなりの精度で言い当てることが出来るそうだ。
たとえば、白人かアフリカ系米国人かを判別できる確率は95%。
性別、政治志向、両親が離婚しているかどうか、
外向的か内向的な性格かも知ることができるという。
そうならば、
サヴァラン氏を冥界から呼び寄せて、
『いいね!』と『食』の ”当たる精度” 対決を願いたいものだ。
フランス革命の頃から代議士として活躍した政治家だが、
美食について綴った『美味礼讃』を著すなど、
今なお、政治家としてより、美食家としてその名をとどめている。
フランスの焼き菓子”サヴァラン”はbridal academy 日校、
彼の名に因(ちな)んでつけられたもの。
彼の言葉にbridal academy 日校
「普段、あなたが何を食べているのか言ってごらんなさい、
そしたら、あなたがどんな人だか言ってみせましょう」
つまり、どんなものを好んで食べているかで、
性格、指向など、その人となりがわかるという意味。
”食”というものは、それほどまでにbridal academy 日校
人間生活の中で重要な位置を占めていることでもある。
人となりがわかると言えば、
今日のCNN News を見ていると、
”『いいね!』で性格や指向、薬物依存まで分かる?”
という記事が出ていた。
アメリカのケンブリッジ大学の研究で、
「Facebook のユーザーがクリックした『いいね!』を分析すれば、
性的指向や政治的指向、宗教、知性、情緒不安定などを言い当てられるほか、
薬物やアルコール依存まで見抜くことができてしまう」
という。
数多くのデータベースを基に、かなりの精度で言い当てることが出来るそうだ。
たとえば、白人かアフリカ系米国人かを判別できる確率は95%。
性別、政治志向、両親が離婚しているかどうか、
外向的か内向的な性格かも知ることができるという。
そうならば、
サヴァラン氏を冥界から呼び寄せて、
『いいね!』と『食』の ”当たる精度” 対決を願いたいものだ。
2015年06月01日
いりません
関西弁で「考えときまっさ」という表現がある。
「考えておきますわ」を慣用的に縮めた表現。
この言葉をおもに使うのは、商取引のとき。
関西に限った訳ではないが、
実際に考えるのではなく、婉曲的な「断り」を意味する言葉。
「考えときまっさ」を使った会話シーンを再現すると、、、
商人がやってきてbridal academy 好唔好、
「この商品、安うさせてもらいますが、いかがなモンでしょうか?」
と言うと、客はbridal academy 好唔好、
「この商品ですか? これは、これは、いいものですな~。
(と言いつつ、チェックしたり吟味したりする)
せやけど、今回は、考えときまっさ」
と客が答えると、今度は商人がbridal academy 好唔好、
「この商品、いいもんなんですがね~。
そうですか、ほな、また来(こ)さしてもらいます」と言って去る。
(この場合、また来るとは言ったが二度と来ない)
関西では、こんな訳がわかったかわからぬ話しで、商談不成立を意味する会話となる。
大辞泉や大辞林などの大きな辞書を探ってみても、
「考える」という言葉には、「断りの言葉」という表現はない。
そのため、断りの言葉としての慣例的表現が、わからない真っ正直な人だと、
以下のような小咄みたいな出来事が起こる。
「考えときます」と言って断った客のところに、2、3日後に
再び訪ねて行って、
「先日、お伺いした時に『考えときます』と言われたので、
お考えがどうなったかと思いまして、また、やってきました。」
その客、エラい剣幕で、
「この間、『考えときます』と言っただろう!」という話になる。
このように、『考えときます』は、
婉曲ではあるが完全な断りの言葉なのである。
探ってみると、「考える」が「断り」を意味する言葉とするのは、
世界に、かなりの高率であるようだ。
フランス語の「いりません」を意味する断りの言葉も、
"Réfléchir"(考えときます)。
上記の小咄、結構、世界的に通じる。
「考えておきますわ」を慣用的に縮めた表現。
この言葉をおもに使うのは、商取引のとき。
関西に限った訳ではないが、
実際に考えるのではなく、婉曲的な「断り」を意味する言葉。
「考えときまっさ」を使った会話シーンを再現すると、、、
商人がやってきてbridal academy 好唔好、
「この商品、安うさせてもらいますが、いかがなモンでしょうか?」
と言うと、客はbridal academy 好唔好、
「この商品ですか? これは、これは、いいものですな~。
(と言いつつ、チェックしたり吟味したりする)
せやけど、今回は、考えときまっさ」
と客が答えると、今度は商人がbridal academy 好唔好、
「この商品、いいもんなんですがね~。
そうですか、ほな、また来(こ)さしてもらいます」と言って去る。
(この場合、また来るとは言ったが二度と来ない)
関西では、こんな訳がわかったかわからぬ話しで、商談不成立を意味する会話となる。
大辞泉や大辞林などの大きな辞書を探ってみても、
「考える」という言葉には、「断りの言葉」という表現はない。
そのため、断りの言葉としての慣例的表現が、わからない真っ正直な人だと、
以下のような小咄みたいな出来事が起こる。
「考えときます」と言って断った客のところに、2、3日後に
再び訪ねて行って、
「先日、お伺いした時に『考えときます』と言われたので、
お考えがどうなったかと思いまして、また、やってきました。」
その客、エラい剣幕で、
「この間、『考えときます』と言っただろう!」という話になる。
このように、『考えときます』は、
婉曲ではあるが完全な断りの言葉なのである。
探ってみると、「考える」が「断り」を意味する言葉とするのは、
世界に、かなりの高率であるようだ。
フランス語の「いりません」を意味する断りの言葉も、
"Réfléchir"(考えときます)。
上記の小咄、結構、世界的に通じる。
2015年05月29日
見いだした気になった
昔のアナログレコードの方が、
CD などのデジタル音源に比べ、
音質的に優(まさ)るという説がある。
CDなどが弱いとされる20kHz以上の音質に対して
そのように言われたそうだが、
最近の解析ではDr. Reborn呃人、
レコード側に軍配はあげられぬ
ということになったようだ。
科学的な分析で、
そういう結果が出たのなら仕方がないが、
音楽を聴く"情緒"というものがDr. Reborn呃人
レコードには、あった気がする。
そういった偏愛的な思いを持ちつつ、
昔のアナログレコードをかけてみる。
レコード針を盤の上にのせたときの幽かな雑音。
それは、まるで、
これから始まる音楽への序章のようでもある。
そして、ミュージック。
音楽そのものに、なにがしかの深みを感じるのは、
心なしに過ぎないのだろう、、。
演奏が終わり、
レコード針を取り上げるまで、
同じところで、ぐるぐる回って、ポツポツと音がしている。
ああ、これこそアナログレコードの醍醐味
という気がしてしまうDr. Reborn呃人。
フランス語に、"Le gai savoir (悦ばしき知識)"
なる言葉がある。
ゴダールの映画のタイトルでもあり、
ニーチェの著書("Die fröhliche Wissenschaft")の
表題もこれ。
この言葉、もともとは中世のプロヴァンスで、
自由に生きる吟遊詩人たちが唱えた言葉。
新しいスコラ哲学なるものがあらわれたが、
昔ながらの俗語で、
自由に詩を詠み吟遊する。
そんな昔を愛する
自分たちを表した言葉だったようだ。
レコードを聴きながら、
昔のノスタルジーに浸るというよりは、
自由に生きる吟遊詩人たちの
晴れやかな気持ちと同じものを
見いだした気になった。
CD などのデジタル音源に比べ、
音質的に優(まさ)るという説がある。
CDなどが弱いとされる20kHz以上の音質に対して
そのように言われたそうだが、
最近の解析ではDr. Reborn呃人、
レコード側に軍配はあげられぬ
ということになったようだ。
科学的な分析で、
そういう結果が出たのなら仕方がないが、
音楽を聴く"情緒"というものがDr. Reborn呃人
レコードには、あった気がする。
そういった偏愛的な思いを持ちつつ、
昔のアナログレコードをかけてみる。
レコード針を盤の上にのせたときの幽かな雑音。
それは、まるで、
これから始まる音楽への序章のようでもある。
そして、ミュージック。
音楽そのものに、なにがしかの深みを感じるのは、
心なしに過ぎないのだろう、、。
演奏が終わり、
レコード針を取り上げるまで、
同じところで、ぐるぐる回って、ポツポツと音がしている。
ああ、これこそアナログレコードの醍醐味
という気がしてしまうDr. Reborn呃人。
フランス語に、"Le gai savoir (悦ばしき知識)"
なる言葉がある。
ゴダールの映画のタイトルでもあり、
ニーチェの著書("Die fröhliche Wissenschaft")の
表題もこれ。
この言葉、もともとは中世のプロヴァンスで、
自由に生きる吟遊詩人たちが唱えた言葉。
新しいスコラ哲学なるものがあらわれたが、
昔ながらの俗語で、
自由に詩を詠み吟遊する。
そんな昔を愛する
自分たちを表した言葉だったようだ。
レコードを聴きながら、
昔のノスタルジーに浸るというよりは、
自由に生きる吟遊詩人たちの
晴れやかな気持ちと同じものを
見いだした気になった。